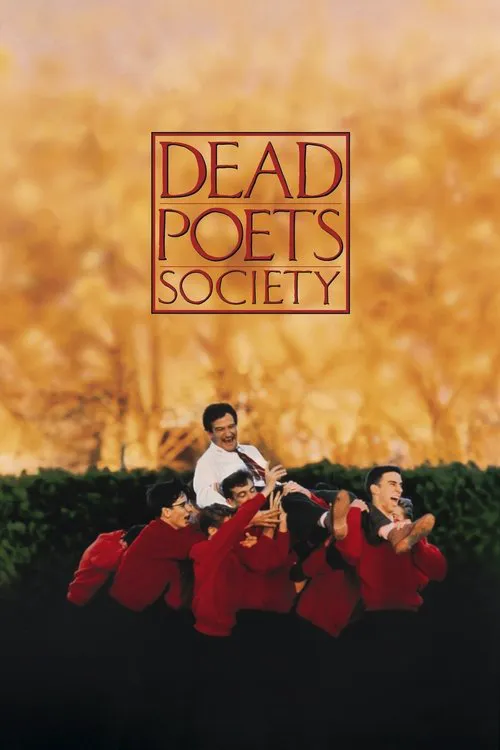いまを生きる
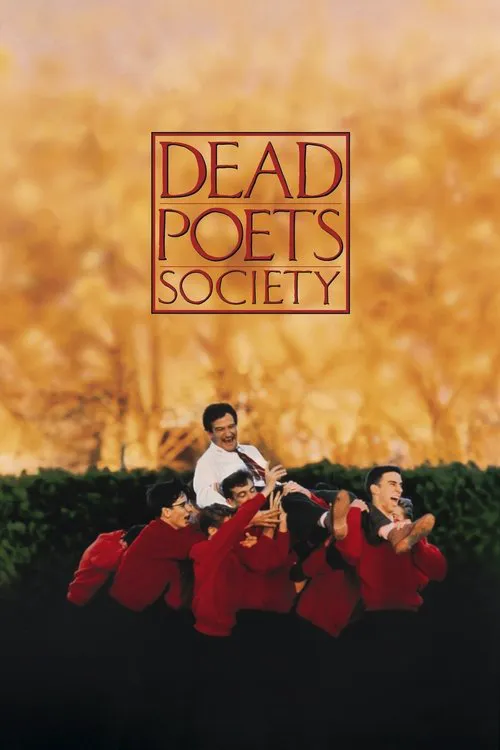
あらすじ
舞台は1950年代、ニューイングランドの名門校ウェルトン・アカデミー。伝統と保守を重んじる寄宿学校で、映画『いまを生きる』は、若き生徒たちと型破りな英語教師、ジョン・キーティングの変革的な関係を探求する。ロビン・ウィリアムズが演じるキーティングは、刺激的で型破りな教育者であり、学校の因習的で息苦しい雰囲気を根底から揺さぶる。 ウェルトンに着任すると、キーティングは生徒たちの生活に関連する、魅力的で刺激的な学習環境を作ることに着手する。彼は教科書からの講義という伝統的な方法を避け、代わりに生徒たちが批判的に考え、彼らの周りの世界を探求することを奨励する。キーティングは自由な精神の持ち主であり、生徒たちが詩の美しさと力を直接体験し、新鮮な目と心で世界を見るように鼓舞することを願っている。 キーティングのクラスの生徒の中には、トッド・アンダーソン(イーサン・ホーク)、チャーリー・ダルトン(ゲイル・ハンセン)、ニール・ペリー(ロバート・ショーン・レナード)、リチャード・キャメロン(ディラン・クスマン)がいる。順応性と伝統を重んじる社会で育ったこれらの若者たちは、当初キーティングの大胆な手法を軽視している。しかし、彼らはすぐに彼の伝染的な熱意と、彼ら自身の創造性を探求するように促す彼の能力に惹かれていく。 キーティングの影響は、英語の授業にとどまらない。彼は少年たちにリスクを冒し、現状に挑戦し、今を生きる(carpe diem)ように勧める。彼の教えを通して、彼は彼らが彼ら自身の声を開発し、世界に対する彼らのユニークな視点を発見するのを助ける。生徒たちが彼らの個性に自信を持つようになるにつれて、彼らはウェルトン・アカデミーの厳格で抑圧的な環境の権威と価値観に疑問を持ち始める。 校長のゲイル(ノーマン・ロイド)は、ウェルトンの時代遅れで不寛容な価値観の体現者である。彼はキーティングを学校の伝統的な秩序への脅威とみなし、彼を失脚させようと決意する。ゲイルは、柔軟性の欠如、権威への独断的な固執、個性の抑制など、伝統的な制度的思考の否定的な側面を体現するキャラクターである。 キーティングの影響が学校中に広まるにつれて、校長は彼に対してますます敵意を抱くようになる。ゲイルの行動は、何人かの少年たちが彼の権威に反抗し、ウェルトンの生徒たちを支配する厳格な規則や行動規範に疑問を抱いていることを知ると、さらに執念深くなる。キーティングとゲイルの対立は、英語教師が生徒たちに植え付けた知的自由と創造性の精神を守ろうとする中で、危機的な状況に達する。 映画の最も痛切な側面の一つは、自分の居場所を見つけようと苦闘している若い生徒ニール・ペリーの物語である。ニールは必死に彼自身の芸術的才能を抑制しようとしているが、それは彼の支配的な父親によって認められていない。キーティングは青年の中に大きな可能性を見出し、演技への愛情を追求するように勧める。悲劇的なことに、ニールの願望は、彼の家族の息苦しい期待とウェルトンの抑圧的な雰囲気によって、最終的に打ち砕かれる。 学期が終わるにつれて、生徒たちはキーティングに最後の別れを告げるために鐘楼に集まる。ほろ苦い瞬間の中で、若者たちは彼らの愛する英語教師に敬意を表し、彼が教えた教訓への感謝の意を表する。映画は、生徒たちが彼らの経験によって永遠に変化した若者たちのグループを残して、キーティングがウェルトンを去ることで終わる。 キーティングのカリスマ的な存在を通じて、ウェルトン・アカデミーは、1950年代の社会的な緊張と文化的な変化の縮図となる。個性、自由な表現、そして教育の力を探求する映画は、今日に至るまで観客の共感を呼び、映画『いまを生きる』をアメリカ映画の時代を超越した名作としている。ロビン・ウィリアムズの勇敢なジョン・キーティング役としての忘れられない演技は、俳優の驚くべきキャリアにおける映画の地位を確固たるものにし、自己表現と非順応の映画の永続的なテーマは、新しい世代の視聴者を鼓舞し続けている。
レビュー
おすすめ