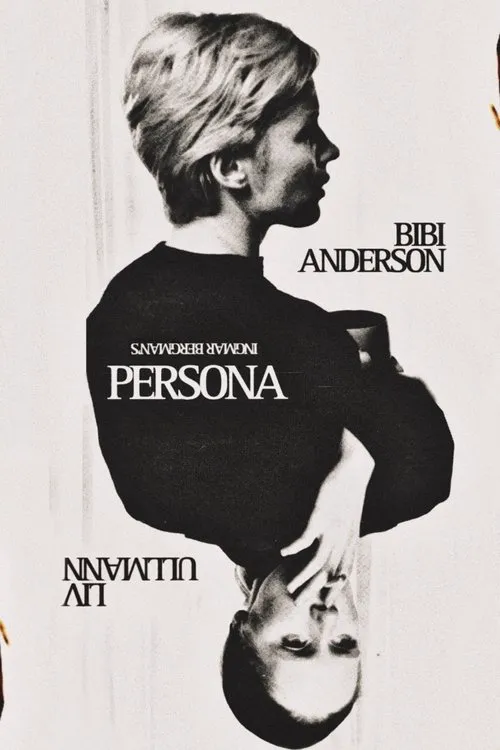ペルソナ
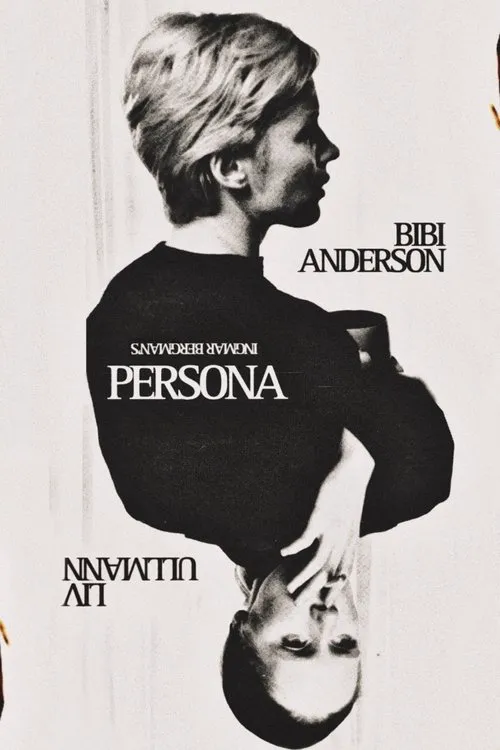
あらすじ
イングマール・ベルイマン監督の1966年の心理ドラマ『ペルソナ』では、若い看護師アルマが、突然話すことをやめてしまった隠遁女優エリザベス・ヴォーグラーの世話に苦労する。この映画は、アイデンティティ、孤立、そして人間という状態に関する複雑で哲学的な探求である。 物語は、ビビ・アンデション演じるアルマから始まる。彼女は、不可解な症状を発症し、話す能力を失った、リヴ・ウルマン演じる有名な女優エリザベスの世話を任された看護師だ。表面的には、エリザベスは完璧な肉体的健康状態にあるように見えるが、彼女の沈黙は心を乱し、不可解である。アルマは、人里離れた別荘でエリザベスの見守りを任されるうちに、若い看護師は、謎めいた患者にますます惹かれていることに気づく。 当初、アルマはエリザベスを会話に引き込もうと試み、彼女を沈黙から抜け出させようと期待する。しかし、アルマの不満とは裏腹に、エリザベスは頑なに口を閉ざし、質問に答えたり、会話に応じたりすることを拒否する。このことが二人の女性の間に不安な力関係を生み出し、アルマはエリザベスの心の壁を打ち破ることにますます執着していく。 アルマがエリザベスの世話を続けるうちに、彼女は自分自身のアイデンティティを維持するのに苦労していることに気づく。エリザベスの沈黙は、アルマ自身の内省のきっかけとなり、自分自身の存在意義や目的を疑問視させる。孤独、孤立、そして断絶の感情と格闘するアルマ自身の精神が、一連の断片的で夢のようなシーンを通して展開されていく。 同時に、エリザベスの沈黙は一種の謎となり、アルマを思索と幻想の世界へと引き込む。アルマの想像力は、エリザベスの動機や生い立ちを理解しようとするうちに、暴走する。エリザベスの過去の痕跡が、個人的な悲劇や感情的な混乱によって特徴づけられた、複雑で波乱に満ちた歴史を示唆する一連の回想シーンの形で現れる。 日々が過ぎるにつれて、アルマ自身のアイデンティティとエリザベスのアイデンティティの境界線が曖昧になり始める。アルマは、まるで二人の女性が一種の精神的な絆を形成したかのように、エリザベスの感情状態にますます巻き込まれていくことに気づく。このアイデンティティの曖昧さは、自己と他者の本質、そして人間のつながりの複雑さについて疑問を投げかける。 この映画全体を通して、ベルイマンは夢のような雰囲気を作り出すために、数多くの映画的テクニックを用いている。カメラは顔に留まり、表情や感情の微妙な変化を捉える。長回しと流れるようなカメラワークは、流動性と内省の感覚を生み出し、観客をアルマとエリザベスの内なる世界へと引き込む。 『ペルソナ』の最も印象的な側面の1つは、アイデンティティの複雑さの探求である。アルマとエリザベスの交流を通して、この映画は、自己の本質、それがどのように形成されるのか、そしてどのように表現できるのかという疑問を提起する。アルマの自己認識がエリザベスとの関係において絶えず交渉、再交渉されるように、アイデンティティは断片的で、複雑で、常に変化しうるものであることがわかる。 最終的に、『ペルソナ』は、一見無意味な世界における意味とつながりの探求についての映画である。アルマとエリザベスの関係を通して、人間がいかに互いにつながろうとするか、多くの場合、断片的で不完全な手段を通してつながろうとするかがわかる。映画が終わるとき、私たちは答えよりも多くの疑問を抱えているが、沈黙と孤立の中にさえ、発見されるのを待つ深い人間のつながりがあるという感覚が残る。 『ペルソナ』全体を通して、ベルイマンの哲学的で詩的なビジョンは、深みとニュアンスの感覚を生み出し、観客を複雑で謎めいた世界へと引き込む。アイデンティティ、孤立、そして人間のつながりに関するこの映画の探求は、最初に公開されたときと同じように、今日でも強力で示唆に富むものである。
レビュー
おすすめ