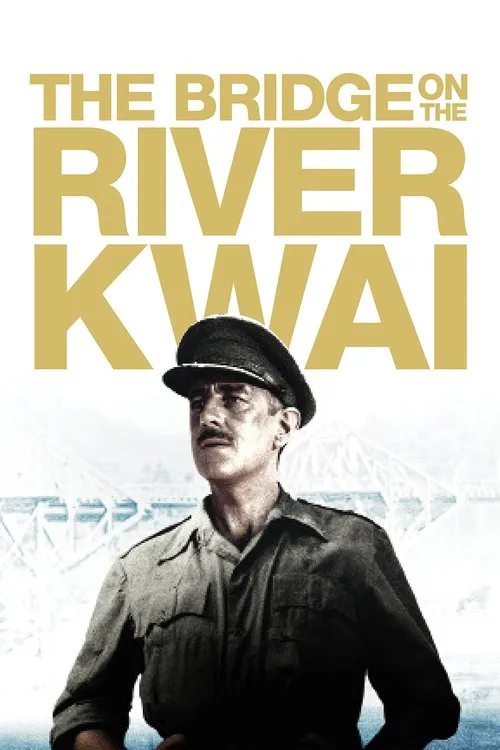戦場にかける橋
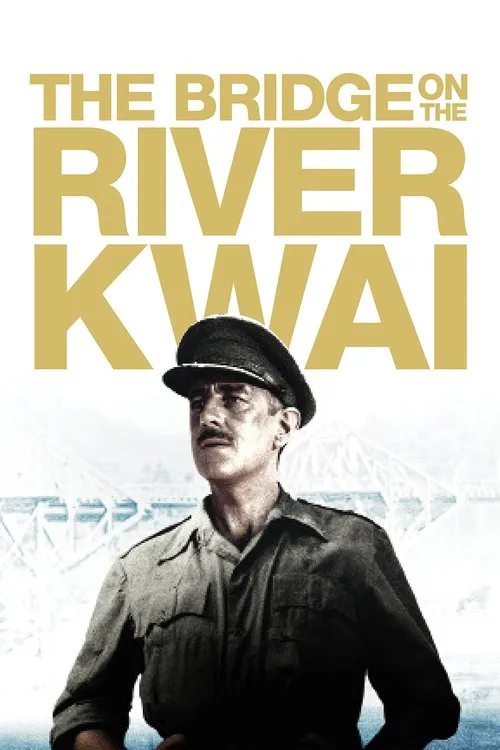
あらすじ
第二次世界大戦を背景に、『戦場にかける橋』は日本軍占領下のビルマで橋の建設を強制されたイギリス人捕虜(POW)の経験を中心に展開されます。この映画は、イギリス兵、特にニコルソン大佐の心理的な葛藤を描いており、彼らは捕虜としての義務と忠誠心、そして自己の行動の道徳的意味合いの間で苦悩します。 物語は、ビルマ戦線で日本軍に捕らえられたイギリス軍将校の一団の捕虜生活から始まります。その中には、厳格で誇り高いイギリス軍人であり、義務感が強いニコルソン大佐がいます。指揮官である斎藤大佐は、捕虜たちにクワイ川に橋を建設させようと決意しています。その橋は、物資や兵士の輸送を容易にし、日本軍の戦争遂行を支援することになります。 当初、状況は絶望的に見え、捕虜たちは過酷な捕虜生活の現実に直面します。しかし、ニコルソン大佐が指揮を執ると、彼は異なるアプローチを取ることを決意します。暴力や脅迫によって規律を植え付けるのではなく、威厳と目的意識を持って捕虜たちを率いることを選びます。彼のモットーである「この橋は今やイギリスの領土の一部であり、完成させる」は、彼らが任務に着手する際の捕虜たちの合言葉となります。 橋の建設が進むにつれて、ニコルソン大佐と部下の間には緊張が高まります。一部のイギリス兵は指揮官の動機に疑問を持ち、またある者は敵のために働かされているにもかかわらず、自分たちの仕事に誇りを持つようになります。彼らは橋を、敵に協力するための道具ではなく、自分たちの創意工夫と職人技の証だと考えます。 一方、ニール大佐率いるアメリカ情報部員の一団がその地域に到着します。彼らは橋を破壊し、日本の補給路を混乱させることを目的とし、その過程でニコルソン大佐と彼の部下を深刻な危険にさらします。一方、斎藤大佐は、捕虜たちが互いに協力し合っていることに疑念を抱き、反乱を企てているのではないかと疑い始めます。 物語が進むにつれて、ニコルソン大佐は橋の完成にますます執着していきます。プロジェクトへの彼の執着は、仲間の捕虜たちに奇妙な影響を与え、彼らは橋を自分たちの義務と目的意識の延長として見始めるようになります。彼らはそれを、敵を支援するための道具ではなく、日本軍捕虜に対する抵抗の象徴として捉えています。 しかし、橋の完成が間近に迫ったとき、ニール大佐とその部下は橋を破壊する計画を立てます。彼らの一部は日本軍の本部に侵入し、橋を破壊工作し、大爆発を引き起こします。橋の職人技に感銘を受けていたニコルソン大佐は、橋の破壊の知らせに打ちのめされます。 物語の終盤、ニコルソン大佐は愛する橋の残骸に閉じ込められていることに気づきます。彼は構造物全体を破壊する爆弾を起爆させようとします、たとえそれが自分の命を犠牲にすることを意味するとしても。しかし、爆弾が爆発しようとしたまさにその時、斎藤大佐が現れてそれを解除するように命じます。斎藤大佐は橋をイギリスのプライドと職人技の象徴とみなし、ニコルソン大佐が残ることを許してでもそれを保存することを決意します。 映画は、イギリスの王冠とその価値観への最後の忠誠行為としてニコルソン大佐が斎藤大佐を殺害し、斎藤大佐の亡骸の上にニコルソン大佐が立っている場面でクライマックスを迎えます。映画は、打ち砕かれ、崩壊した男、ニコルソン大佐として終わります。彼は最終的に、彼に何がなされたのかの背後にある意味を理解します。
レビュー
おすすめ