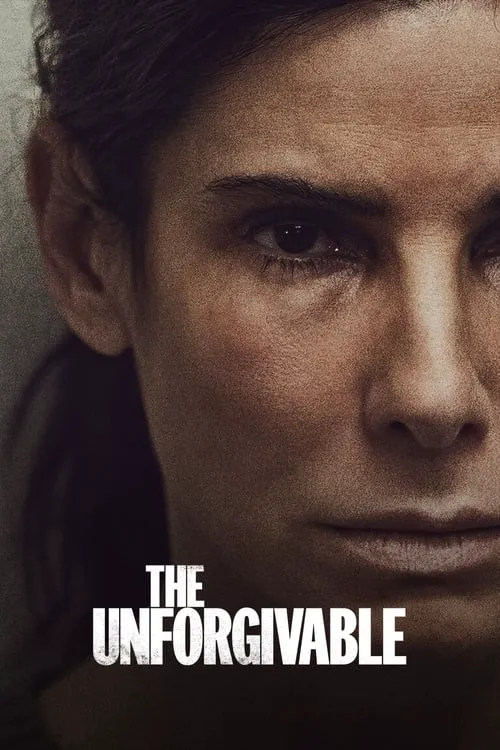許されざる者
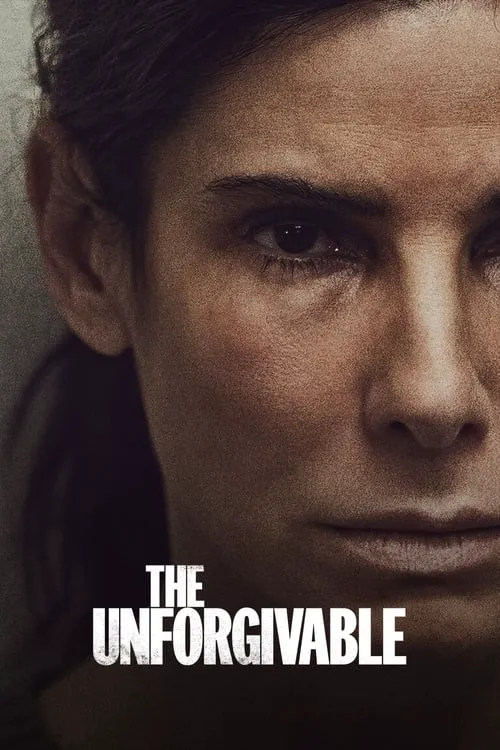
あらすじ
元受刑者のレイチェル・キムは、刑務所の独房から出て、ニューヨークの肌寒い冬の朝を迎える。彼女は15年もの間、刑務所にいた。きっかけは、抑制のきかない怒りにかられて犯した罪。彼女を嫌がらせていた警察官を殺してしまったのだ。その瞬間、彼女の人生は永遠に変わり、その後の彼女の軌跡も永遠に変わってしまった。今、彼女は矯正施設の容赦ない壁によって心を閉ざされた女性であり、かつて活気に満ちていた精神は、風の中の灰のようにゆっくりと消えていく。 釈放されたレイチェルは、ブルックリンにあるハーフウェイハウスに報告することになっている。ハーフウェイハウスとは、彼女のような女性が社会に復帰するのを容易にするための移行施設だ。そこは、厳格な規則、終わりのない講義、そして魂を押しつぶすような官僚主義の場所だ。ソーシャルワーカーのメアリーは、受刑者を街に戻すことのリスクを意識しながら、同情と警戒心が入り混じった表情で彼女を迎える。レイチェルは手続きを受ける中で、一連の尋問、健康診断、心理評価を受ける。これは、彼女の釈放準備ができているかどうかを判断するための評価の試練なのだ。 レイチェルの社会復帰は、広範な疑念と敵意をもって迎えられる。彼女が出会うのは、見慣れないながらも敵意のある世界だ。そこでは、彼女の存在がささやきと鋭い視線を浴びせる。近所の人や通行人は、彼女を嫌悪感と哀れみの混じった目でちらりと見ずにはいられない。まるで彼女が異質な生物であり、贖いや許しに値しない存在であるかのように。道行く見知らぬ人は、彼女を避けるように歩道を横切り、彼女と周囲の世界との間を視線が行き来し、彼女の脆い外見の裏に潜む危険の可能性を推し量る。 レイチェルがハーフウェイハウスでの新しいルーチンに慣れていく中で、それぞれの傷と回復の物語を抱えた女性たちのコミュニティに出会う。そこには、運命の残酷な気まぐれに免疫を持ちながらも、希望の光にしがみついているベス、DV夫に見捨てられた後も子供たちを守ろうと奮闘している20代前半の母親サマンサ、長年の自己破壊の末に新しい道を探しているリサがいる。彼女たちは、共有する経験や苦労、そして新たなスタートを切ろうとする揺るぎない決意によって結びつき、ありそうもない支援システムを形成する。 レイチェルのソーシャルワーカーであるメアリーは、彼女が迷路のような規則や規制の中を進む中で、導きとサポートを提供するライフラインとなる。メアリーの思いやりと理解は、レイチェルを取り巻く無関心や懐疑主義に対する対抗勢力となるが、メアリーの努力さえも、レイチェルのケースの複雑さに直面するにつれて試される。レイチェルのリハビリを擁護する中で、メアリーは贖罪の可能性について、彼女自身の中にあった疑問や恐怖に直面せざるを得なくなる。 困難にもかかわらず、レイチェルは自分の人生を再建し始める。過去の断片をつなぎ合わせ、新たな道を切り開いていく。彼女はウェイトレスとして働き口を見つけ、何年も失っていた目的意識と帰属意識を取り戻す。彼女は高校卒業資格を取り直し、より明るい未来への見通しを改善しようと、GEDプログラムに入学する。そしてゆっくりと、最も大切な人々との関係を再構築し始める。レイチェルの釈放を辛抱強く待っていた妹のエマ、そして叔母の名が恐怖と同義語になっている世界で育った姪のソフィアだ。 しかし、レイチェルの過去の亡霊は消えることを拒否し、いつまでも付きまとう。彼女が殺した警察官の家族は、今も苦い思いと怒りを抱き続け、その憎しみは有毒な染みのように地域社会に染み込んでいる。彼らはハーフウェイハウスの外で抗議活動を行い、レイチェルの地域社会への存在を非難し、殉職した警察官への正義を要求する。彼女が直面する敵意と反感は、一部の傷は決して完全に癒えることはないかもしれない、赦しは、人間の経験の地平線上に現れる掴みどころのない蜃気楼かもしれない、ということを常に思い出させるものとなる。 レイチェルは新たに見つけた自由という複雑な風景を進む中で、彼女自身の精神の暗い側面と向き合わざるを得なくなる。彼女は、暗闇の深淵に落ち、傷つきながらも壊れずに這い上がってきた女性だ。その経験は、美しくも残酷なほど正直な、独特の視点を彼女にもたらした。結局のところ、レイチェルの旅は、贖罪への道は困難と不確実性に満ちているが、許しは愛と同様に、どんなに困難であっても、私たちが毎日できる選択なのだということを痛切に思い出させるものとなる。
レビュー
おすすめ