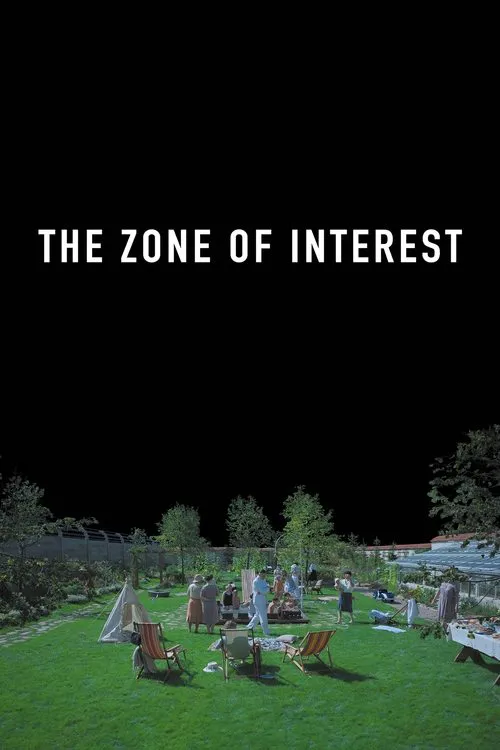関心領域
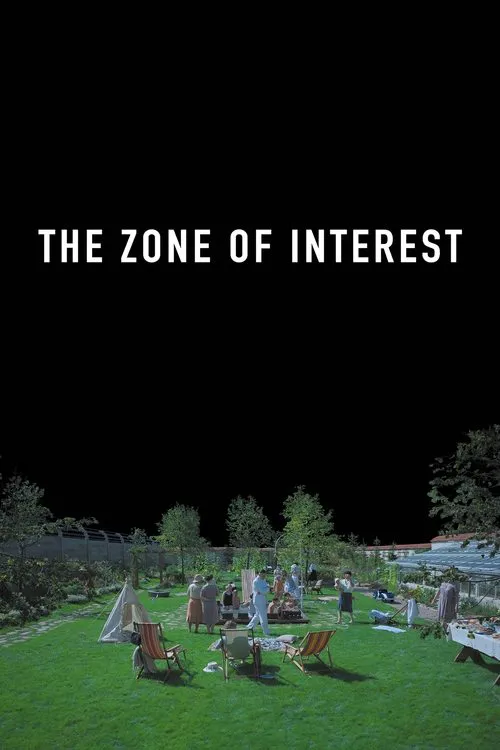
あらすじ
人類史における最も暗い時代を舞台に、マルティン・ジヴェツの心理ドラマ『関心領域』は、第二次世界大戦中にアウシュビッツで行われた最も凶悪な犯罪の責任者たちの生活を、容赦なく見つめる。欺瞞の虚飾を剥ぎ取るような痛烈な物語を通して、ジヴェツは、ドイツ軍高官の戦争への共謀に対する痛烈な批判となる映画体験を創り上げている。 映画の中心となるのは、アウシュビッツ収容所の所長ルドルフ・ヘスである。サスキア・ケイルとアレクサンダー・ベイヤーが印象的な二役を演じるヘスは、ナチス政権への義務と、自分と家族のために理想郷を築きたいという必死の願望の間で引き裂かれる、二面性を持つ人物として描かれる。ヘスが丹念に手入れする庭にカメラがパンすると、血に染まった周辺と文明化された虚飾の対比が顕著になり、彼らの隔離された世界の境界線のすぐ先に存在する恐怖を際立たせる。 ナチス政権の中枢で指揮を執る人物として、ヘスの二重の役割は、戦時中の人類を定義する二律背反の痛烈なメタファーとして機能する。彼の世界では、家族、生活、感情は、ヒトラーの主張を促進することに関係する場合を除き、ほとんど重要ではない。これにより、ヘスは人間味を帯び、観客は彼を平面的で一面的な悪の象徴として見るのではなく、悪名高い加害者と感情的につながることができるようになる。 しかし、この微妙な視点の変化は、答えよりも多くの疑問を提起する。もしヘスが悪魔の化身ではなく、内なる葛藤を抱える多面的な人物であるとしたら、彼が毎日監督する残虐行為の原動力は何なのだろうか?彼は強制的な義務、神話的なアーリア人の理想に応えようとするプレッシャー、あるいはもっと不吉な何かに突き動かされているのだろうか?物語が展開するにつれて、ダニカ・クルチッチが繊細に演じる妻ヘドウィグへの優しさの光が見える。彼らのもろく消えゆくつながりは、ヘスを人間性に固定し、視聴者に脱感作がどのように可能になるのかを熟考させる。 ジヴェツがヘスと妻の関係に焦点を当てることで、特異な均衡が明らかになる。二人ともジェノサイドの永続化に加担しているにもかかわらず、ヘドウィグは感情的な幸福が自己嫌悪と絶望から完全な放棄へと悪化した、断片化された空間に存在し、そのため彼女のキャラクターは感情がちらつくことを一瞬許すことを恐れない。逆に、ルドルフはこれらの苦痛な矛盾と格闘し、増大する不安をほぼ完全に埋め、毎朝する必要があることをいつでも実行する準備ができている。 したがって、『関心領域』は、私たちが住むこの二重生活世界の不安で暗い側面を掘り下げる。ヘスが残虐行為の現場の隣で理想的な家庭生活を探すことに焦点を当てることで、ジヴェツの見事な演出は、制度化され、残虐化された形態の暴力に伴う複雑な力関係を蒸留する。私たちが経験するのは、残忍な専制政治の上に築かれた社会に対する冷酷で思いやりのある解剖であり、そこでは、むき出しの現実と格闘するしかなくなると、普通の礼儀正しさは決してそのままではいられない。したがって、このかつて忘れ去られた風景に非常に固有の、和解できないコントラストを例示している。
レビュー
Thiago
There's no deliberate criticism or vilification, it just quietly shows you the daily life of a quintessential old-school Nazi, which is all the more gut-wrenching.
Callie
Cold, powerful, precise execution; unwavering commitment to action. I'd give it the Palme d'Or.
Asher
Approaching the Holocaust from a completely opposite direction, *The Zone of Interest* finds another kind of “shock” in the trivial, mundane realities of a concentration camp officer's family life. It reminds us that Auschwitz, so often portrayed as a black and white hell (as in *Schindler's List*), that black and white image belonging only to history, was once the present. It wasn't only darkness and bloodshed. On the contrary, the Jews died in a spring that continued to arrive, the bouquets remained vibrant, and song and dance created a facade of prosperity. The cruelty of humanity lies not in Auschwitz being a pre-existing purgatory, but in the fact that each concentration camp was surrounded by an " earthly paradise". Grazer's efforts here are nothing short of...
Lillian
Completely polar opposite in pacing compared to *Son of Saul*, yet both are concerned with acoustics and off-screen space. This film offers a fourth-level perspective on the Holocaust, stemming from Glazer's audacious choice of viewpoint, providing a fresh entry point into the subject. The sound design is exceptionally outstanding, with the sound sources from the concentration camp acting almost as a constant "background noise." Łukasz Żal's cinematography is a major contribution (perhaps the best at stationary shots DP in this era), bringing genuine innovation to similar themed works through its filming approach, the ultra-sharp digital photography scrutinizing every inch and creating a kind of "Nazi aesthetic" within the highly rigorous compositions.
Clara
If it weren't for the final scene's jump through time, I'd only give it three stars. The film's consistent chilling detachment creates a spectacle: those living through history are forever ignorant of how posterity will judge them, hence their seeming tranquility. The wife merely hopes her husband won't be transferred; their aspirations for a happy life are, in truth, quite understandable. With this kind of narrative approach, it's essential to establish a historical perspective and draw a conclusion at the end. In Auschwitz, the tour guide mentions that every inch of the ground contains Jewish ashes and fragments, while in the postwar trials, Nazi officers' families claim they were unaware of what was happening behind the walls. Such is the cruelty of history...
おすすめ