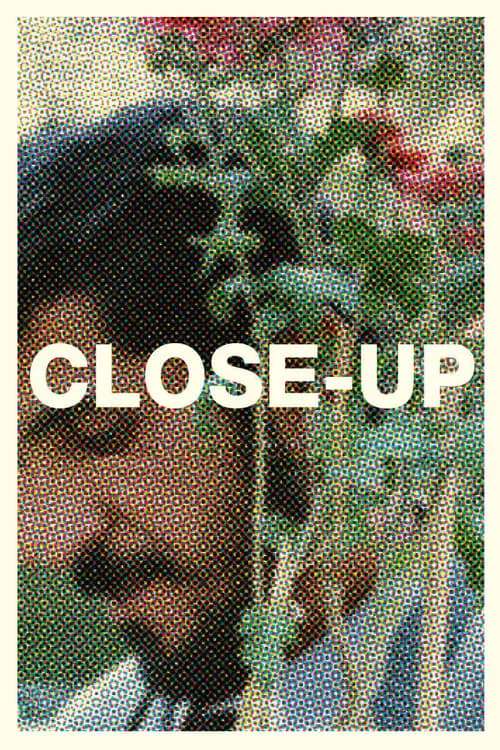クローズ・アップ
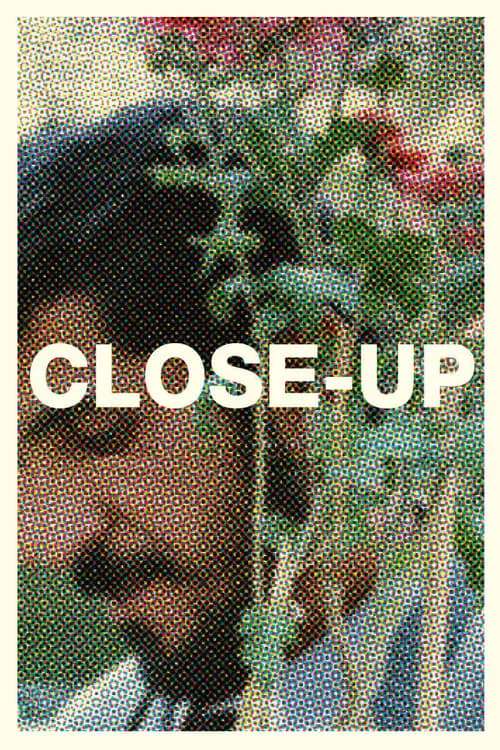
あらすじ
映画「クローズ・アップ」は、20代後半の映画撮影技師と自称するサッビアンを紹介することから始まる。彼は、当時イランの著名な映画監督であったモフセン・マフマルバフ監督による、高く評価された映画「楽園の色」に夢中になる。イラン映画界のもう一人の有名な監督であるエブラヒム・ハタミキアと、モフセン・マフマルバフ自身も、芸術への貢献を高く評価されている。サッビアンは、2人の子供、ホセインとレイラがいる質素な家庭、ガジャール家に連絡を取り、映画を鑑賞するように誘い、モフセン・マフマルバフとの知り合いが映画製作者の助けになると説明する。 サッビアンは、マフマルバフの最新作に関わっている映画撮影技師であると自称し、マフマルバフと親しい関係にあることを説明することで、ガジャール家の信頼を得る。家族は彼が一緒に来ることを許し、サッビアンは彼らの生活に興味を持ち、映画を通して彼らの日常生活を記録することに興味のある芸術家として振る舞う。時間が経つにつれて、サッビアンはガジャール家の私生活にますます立ち入るようになり、ホセインとレイラに、彼らの存在がマフマルバフの新作映画の完成に不可欠であるとさえ納得させる。 ある日、彼らの信憑性と、モフセン・マフマルバフとのつながりの真実性を確かめるために、サッビアンはホセインとレイラを映画製作者たちと自宅で会わせるように誘う。2人の子供たちは喜んで参加し、マフマルバフが到着するのを楽しみに待つ。しかし、マフマルバフの家に到着すると、そこは混雑して混沌とした場所であり、何時間も待たされる。結局、彼らはマフマルバフが仕事で忙しく、直接会うことができないことを知る。 この事実は、サッビアンの主張に対するガジャール家の疑念のきっかけとなる。家族はすぐに、サッビアンがマフマルバフの親しい関係者ではなく、彼らを欺こうとする詐欺師であるという真実を発見する。サッビアンの欺瞞の背後にある意図は、マフマルバフになりすました罪で逮捕され投獄されるにつれて、表面化する。 この映画は、サッビアンの行動に対する罪状認否と裁判を掘り下げ、ガジャール家を欺いたとして非難する。訴訟を通して、サッビアンは、彼の意図は、短い間、他の誰かになることがどういうことかを体験したいという芸術的な願望に根ざしていると主張し、自己弁護を行う。彼は、自分の動機を、現実と芸術の間の人工的な境界に疑問を投げかける、実存的な探求として説明する。 裁判中には、サッビアンの欺瞞は、単なる自己発見のためではない可能性が示唆される。むしろ、彼は芸術を媒体として、これまでできなかった方法で世界とつながるために利用した。この探求は、芸術の複雑さ、特に現実を表現する役割と、2つの間の境界線を曖昧にする役割を浮き彫りにする。 法廷のシーンは、エブラヒム・ハタミキアやモフセン・マフマルバフなど、事件に関与した実在の人物と、彼らのキャラクターのフィクション化との交流の舞台でもある。彼らは、サッビアンに質問しているように見える。これらのシーンは、事実とフィクションの境界線を曖昧にする。 法廷で繰り広げられる出来事を通して、「クローズ・アップ」は、芸術的表現という概念そのものに挑戦し、芸術を創造することの意味や、現実の真の表現を構成するものなどの疑問を掘り下げていく。裁判が終わりに近づくにつれて、観客はサッビアンの行動を芸術として分類できるのか、彼の試みは人間の状態に対する正当な探求なのか、それとも単に彼の根深い不安の表れなのかを熟考することになる。 この映画はまた、物語の語られる社会的な文脈を反映している。事件当時のイランの社会情勢は重要な役割を果たした。イランの映画製作者は検閲に苦労することが多く、イラン政府が認めた「公式」映画製作者の中には、体制の承認を得られる映画を何とか制作する者もいた。この物語は、政府の規制が芸術的表現に与える影響に関連するテーマを、フィクション化された方法で探求している。 全体として、イランの監督ジャファール・パナヒの映画は、認識と現実、真実と欺瞞、そして存在と芸術の間の緊張を検証するために、多面的なアプローチを採用している。セミドキュメンタリーの手法を採用することで、映画はフィクションと現実の境界線を曖昧にし、観客をサッビアンの自己発見と芸術的探求の旅に誘う。映画ファン必見の作品です。
レビュー
おすすめ