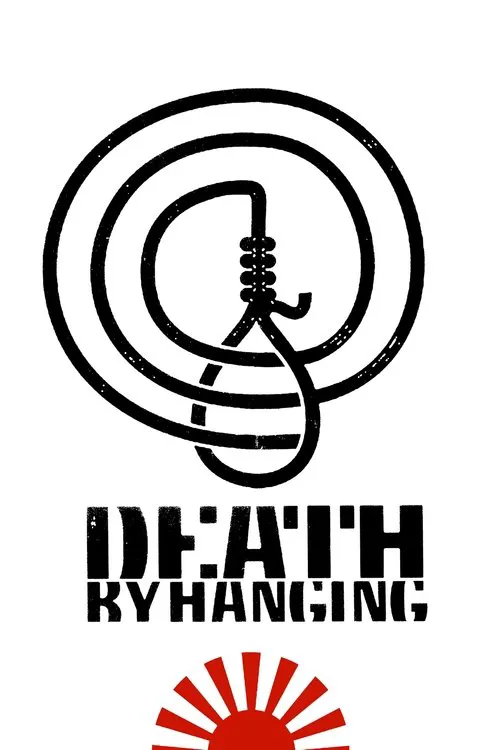絞死刑
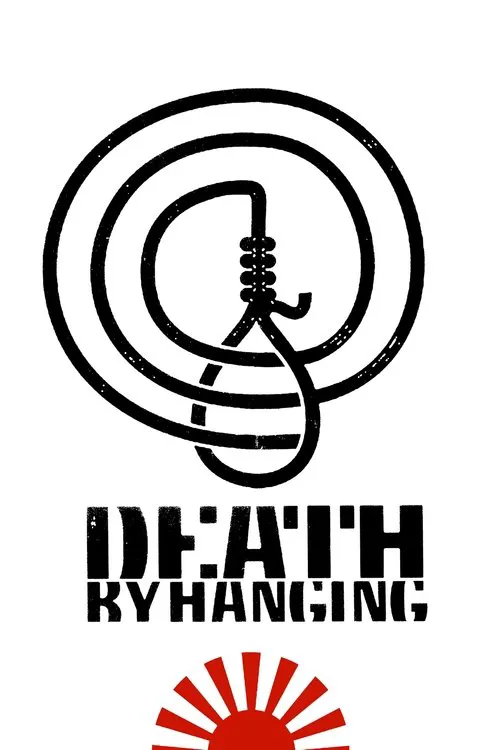
あらすじ
『絞死刑』は、1968年に大島渚が脚本・監督を務めた日本のドラマ映画である。本作はカンヌ国際映画祭で初公開され、叙情的で詩的なスタイルが特徴であった大島の前作とは一線を画す作品となった。『絞死刑』は、ドラマとコメディの境界線を曖昧にする、より実験的なアプローチを採用している。 この映画は、凶悪な犯罪を犯したとして日本で死刑宣告を受けた韓国人男性、柳居(リュウイチ)の物語である。処刑の時が近づくにつれ、柳居の人物像は一連の変化を遂げ、物語の期待を裏切り、道徳そのものの概念に挑戦していく。映画は、柳居が絞首台に連行され、絞首刑に処される場面から始まる。しかし、まさに処刑が執行されようとした時、一連の事故により執行吏は刑を執行できず、柳居は命拾いをする。 当局は何をすべきか分からずパニックに陥り、次に何をすべきか分からなくなる。柳居が法の網をかいくぐるうちに、一連の奇妙で不安な出来事に遭遇し、事態の不条理さを浮き彫りにしていく。映画全体を通して、大島は醒めたユーモアのトーンを用い、それが全体的な不安感と不快感を増幅させている。柳居という人物は、明確なアイデンティティを持たない暗号のような存在として描かれ、戦後日本の矛盾を体現している。 柳居が日本のアンダーワールドをさまよううちに、それぞれが独自の歪んだ世界観を持つ一連の奇妙な登場人物に出会う。これらの登場人物には、柳居に強い魅力を感じる日本人女性、彼を偶像化する騒々しい若者グループ、そして彼を捕獲する任務を負った一連の役人などが含まれる。これらの出会いを通して、大島は戦後日本の暗部を露わにし、隠蔽されてきた社会の弊害を暴露していく。 映画の物語は、その支離滅裂で断片的な構造が特徴であり、それは物語に蔓延する混沌と混乱を反映している。カメラワークも同様に革新的で、静止画、クローズアップ、長回しなど、型破りなテクニックを駆使している。これらのテクニックは、全体的な方向感覚の喪失と不安感を助長し、観客を映画の世界へと引き込む。 『絞死刑』の最も顕著な特徴の一つは、その言語と対話の使い方である。脚本には日本の歴史や文化への言及が散りばめられており、物語に蔓延する方向感覚の喪失と混乱感を強調する役割を果たしている。同時に、その言語はしばしばシュールで夢のようなものであり、現実とファンタジーの境界線を曖昧にしている。この言語の使用は、全体的な不確実性と混沌感を増大させ、観客は何が現実で何がそうでないかを識別することを困難にしている。 映画全体を通して、大島は道徳と正義の本質について様々な疑問を投げかける。柳居という人物は、責任能力のない人物として描かれ、有罪でありながら無罪でもあるという矛盾した存在である。このパラドックスは、道徳は社会的な構築物であり、正義はフィクションであるという考えを強調している。映画の結末も同様にオープンエンドであり、観客は柳居の運命の含意、そして物語のより広範な意味について熟考することになる。 『絞死刑』は、視覚的に印象的であると同時に、知的に挑戦的な映画である。その革新的な言語と物語構造の使用は、道徳や正義といったテーマの探求と相まって、示唆に富み、忘れられない鑑賞体験となっている。実験的な性質にもかかわらず、この映画は長年にわたってカルト的な人気を維持しており、その影響はマーティン・スコセッシやテリー・ギリアムなど、後の映画監督の作品に見ることができる。
レビュー
おすすめ