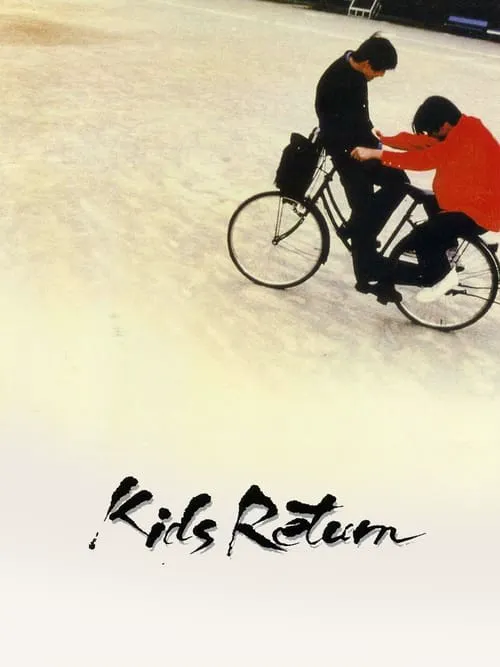キッズ・リターン
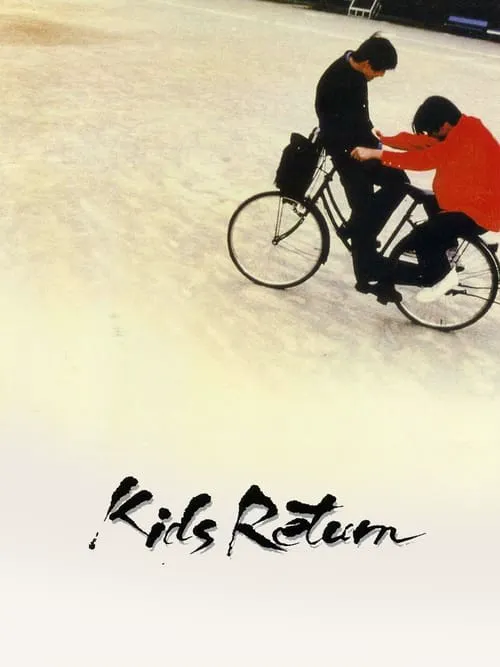
あらすじ
1996年の日本映画『キッズ・リターン』で、監督の北野武と松本omości一は、社会に馴染めず苦闘する二人の高校中退者の姿を、リアルかつ生々しく描いています。物語は、厳格な階層制度や慣習に幻滅したシンジ(演:渋川清彦)とマサル(演:当時「ゴリ」として知られていた、戸賀伊五波の代役、織田裕二)を中心に展開します。 シンジとマサルは、クラスメートをいじめたり、いたずらを仕掛けたりするなど、反体制的な行動に明け暮れます。これは、自分たちの個性を主張し、周囲から期待される従順さを拒否する手段でした。しかし、成長するにつれて、生活費を稼ぎ、自分の進むべき道を見つけなければならないことに気づきます。刺激や冒険への憧れはあるものの、選択肢は限られており、難しい決断を迫られます。 シンジがボクサーになることを決意したのは、肉体的、精神的な鍛錬をしたいという願望に加え、経済的な安定への期待からでした。彼は特に、社会的地位や家庭環境ではなく、純粋な回復力と意志の力によって価値が決まる、無骨で個人主義的なボクシングの世界に惹かれます。シンジの目標は、必ずしもプロのボクサーになることではなく、生活の糧を得て、自尊心を確立することでした。 対照的に、マサルは地元のヤクザ組織に加わり、犯罪者の道を選びます。彼は、安易な金銭、仲間意識、そして、自分と同じように既存の価値観に反発するアウトサイダー集団に所属することに魅力を感じます。マサルが組織犯罪に関わることを決意したのは、衝動的で無鉄砲な選択であり、刺激への渇望と冒険心に突き動かされた結果でした。 物語が進むにつれて、シンジとマサルは、厳しい現実に直面しながら、人生を歩んでいきます。彼らは、貧困、孤独、そして周囲の世界に対する失望感に苦しみます。これらの困難に対処しようとする彼らの試みは、飲酒、喧嘩、その他の悪癖など、自滅的な行動を伴うことがよくあります。 物語が進むにつれて、現実はやはり厳しい世界であり、善と悪の境界線はしばしば曖昧であることが明らかになります。シンジとマサルは、社会の片隅で生き残ろうと苦闘する他の登場人物との複雑な関係に引き込まれます。これらの関係は、優しさ、脆弱性、そして最終的には絶望に満ちています。 『キッズ・リターン』の最も印象的な点の1つは、ティーンエイジャーの不安や幻滅を感傷的に描いていないことです。この映画は、登場人物の経験をロマンチックに美化したり、単純化したりせず、彼らの感情的な葛藤や直面する困難な選択を、生々しく、率直に描いています。 監督の演出と撮影技術も同様に注目に値し、日本の都市裏社会の荒々しく、コントラストの強い美的感覚を見事に捉えています。自然な照明と手持ちカメラの使用が、映画のリアリズムを高め、登場人物の過酷で容赦のない世界に観客を没入させます。 最終的に、『キッズ・リターン』は、シンジとマサルが大人になるという過酷な現実に直面せざるを得なくなる、成長物語として見ることができます。彼らの経験は、社会に馴染めず苦闘する若者が直面する困難を具現化したものであり、若者の生活に対する社会的、経済的な影響や、不確実性と危険に直面して難しい選択をすることの結果について、重要な問題を提起しています。
レビュー
おすすめ