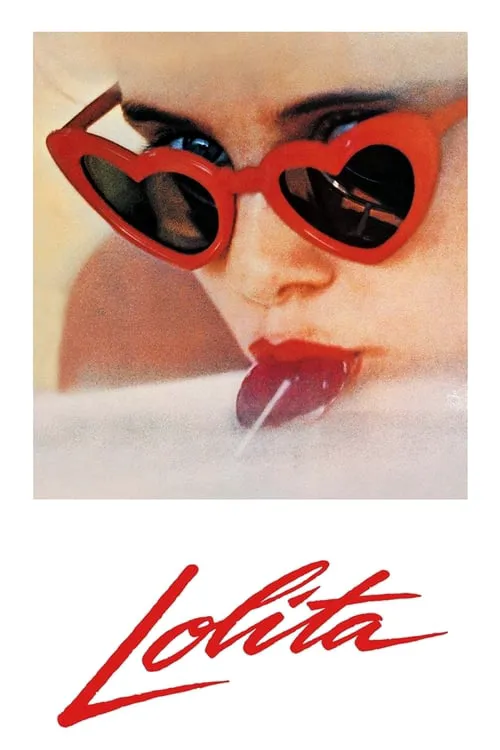ロリータ
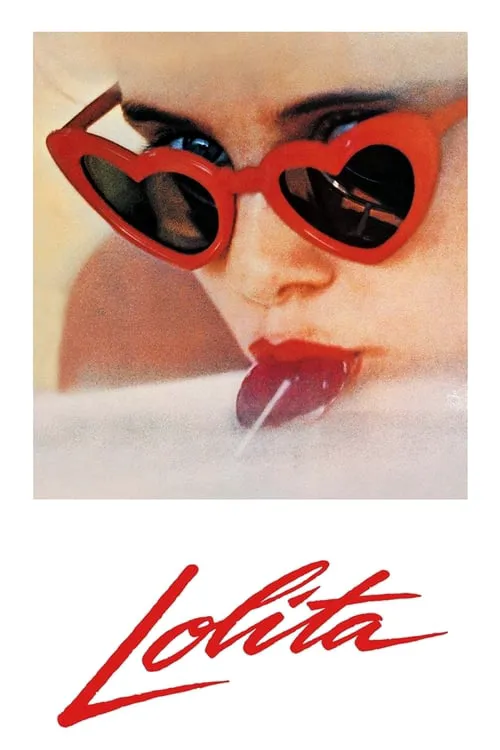
あらすじ
第二次世界大戦後の時代を舞台にした、スタンリー・キューブリック監督による1962年のウラジーミル・ナボコフの小説「ロリータ」の映画化は、強迫観念、道徳、そして人間の本性の暗い側面を探求する、考えさせられる作品です。この映画は、フランスの詩人の伝記を書くために米国にやってきた中年イギリス人小説家、ハンバート・ハンバート(ジェームズ・メイソン演)の物語を描いていますが、彼は国の粗野さと文化の欠如にますます幻滅を感じています。 ハンバートがシャーロット・ヘイズ(シェリー・ウィンタース演)が経営する趣のある下宿に到着したときから、彼の強迫観念への没落が始まります。ハンバートはシャーロットに会うとすぐに、彼女の魅力的で活発な性格に惹かれますが、彼の本当の関心は、彼女の若い娘、ドロレス(スー・リオン演)、愛称ロリータにあります。最初の戸惑いにもかかわらず、ハンバートは自身のゆがんだ欲望に引き裂かれ、その欲望は彼を狂気に近い強さでロリータを追い求めるように駆り立てます。 数か月が過ぎるにつれて、ハンバートはまだ10代のロリータにますます夢中になります。彼は若い少女を手に入れるために、ヘイズ家に潜入するために複雑な欺瞞と操作の網を織り始めます。一方、夫の真の意図を知らないシャーロットは、ハンバートに夢中で、ロリータへの欲望に駆られた彼にとっては迷惑でしかありません。 不幸なことにシャーロットが自動車事故で亡くなると、ハンバートのロリータへの執着は最高潮に達します。シャーロットの死における自身の役割に対する悲しみと罪悪感が入り混じったハンバートは、ドロレスの父親の遺言に従い、父親の友人の世話になるはずのドロレスと結婚しますが、実際には、ドロレスの父親がハンバートに残した最後の遺言には、彼女が自分で選んだ男の世話になるべきだと書かれています。シャーロットの死後、ハンバートは遺言で定められた通り「ハンバート・ハンバート」という名前を名乗り、ロリータの親権と後見権を得ます。 映画は、ハンバートがロリータの愛情深い保護者になりすまし、アメリカの郊外生活という危険な海を航海しようとする中で、ダークコメディの様相を呈します。ハンバートの真の欲望を隠しながら、正常な状態を維持しようと苦闘する中で、彼の見せかけは常に疑問視されます。ハンバートとロリータの関係が深まるにつれて、観客の不安と不快感も増していきます。 映画全体を通して、キューブリックはハンバートの性格の複雑さを巧みに探求し、彼の性格の暗い側面から決して目を背けません。メイソンのハンバートの描写は魅力的でありながら嫌悪感を抱かせ、キャラクターの苦悩する内面の葛藤を揺るぎない精度で捉えています。この内面の葛藤は、スー・リオンの魅惑的な演技とも釣り合いがとれており、彼女はロリータに痛切で忘れがたい、脆弱性と憧れの感覚を与えています。 撮影も同様に印象的で、キューブリックは豪華で鮮やかな色彩を用いて、不安と緊張感を生み出しています。一方、カメラワークは超越した感覚が特徴であり、まるで観客がスクリーンの出来事をハンバートの歪んだ視点を通して観察しているかのようです。長回しと意図的なペース配分によって閉所恐怖症のような感覚が生まれ、観客をハンバートが作り出した悪夢のような世界に引き込みます。 映画がクライマックスに達すると、ハンバートの行動が悲劇的な出来事を引き起こし、最終的に彼の没落につながることが明らかになります。正常な状態を維持しようと最善を尽くしましたが、ハンバートの真の性質は徐々に明らかになり、彼の性格の腐敗した裏側があらわになります。 キューブリックの「ロリータ」は、道徳の本質、愛と強迫観念の曖昧な境界線、そして抑制のない欲望の危険性について、観客に疑問を抱かせる映画です。人間の心の奥底に対する揺るぎない洞察力によって、鑑賞者を不安にさせ、落ち着かなくさせ、しかし最終的には魅了させる人間性の考察作品です。
レビュー
おすすめ