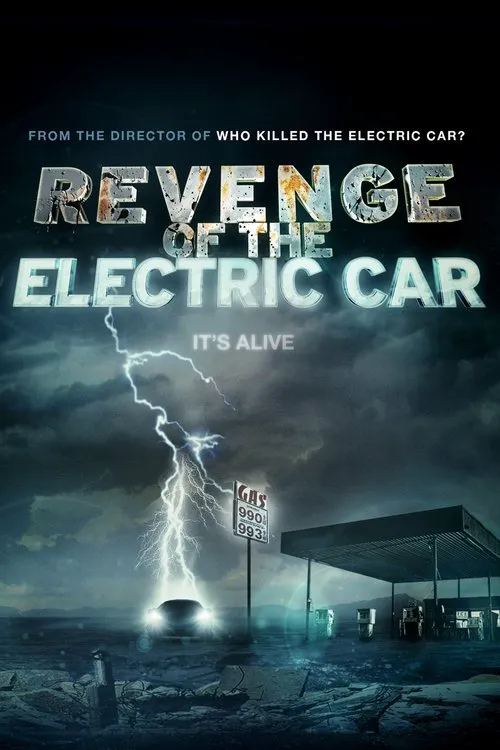電気自動車の逆襲
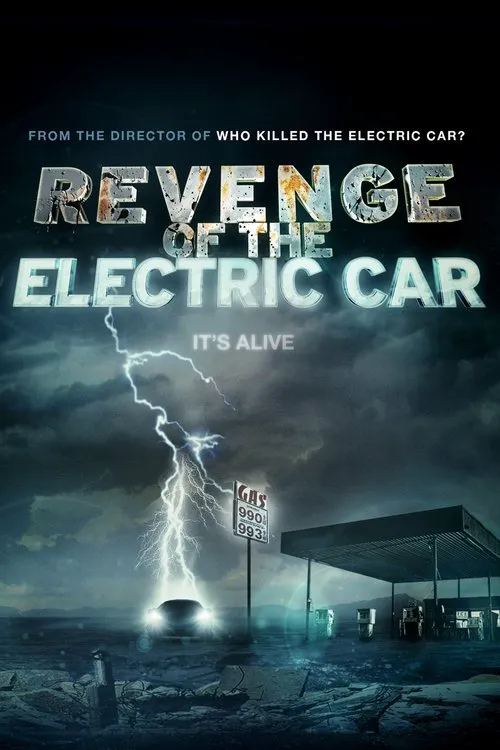
あらすじ
2000年代初頭、電気自動車は非実用的で信頼性が低いとみなされ、自動車業界はガソリン車へと移行していった。クリス・ペイン監督の2006年のドキュメンタリー『Who Killed the Electric Car?』は、政府、自動車業界、エネルギー会社からの反対など、電気自動車の登場を阻む様々な障害を暴露した。それから6年後、新興技術、経済の変化、自動車業界の変革によって変化した状況の中、ペイン監督は消費者市場向けの実用的な電気自動車の量産に向けた新たな動きを記録しようとした。 『電気自動車の逆襲』は、かつて米国で放棄されたコンセプトであった電気自動車という犯罪現場に、視聴者を連れ戻す。この映画は、ゼネラルモーターズのリック・ワゴナーCEOや日産のカルロス・ゴーン会長など、業界の先駆的なプレーヤーが、電気自動車の波に乗るか、既存の戦略を維持するかという戦略的な決断を下すにつれて、自動車セクターで起こっている変革を掘り下げる。同時に、テスラのよう な新しい競争相手は、抜け穴を利用し、急速に進化する電気自動車(EV)セクターに多額の投資をすることで台頭した。 テスラが主流に参入し始めると、カリスマ的なCEOであるイーロン・マスクは、この電気革命の舵取りをすることになった。マスクは、世界初の量産型電気セダン、テスラ ロードスターの生産を構想した。彼は、従来の自動車製造施設を迂回し、代わりにシリコンバレーを拠点とした革新的なプロセスを通じて車両を設計、製造、販売するという型破りなアプローチをとった。 同時に、かつて支配的だった米国の自動車メーカー、シボレー ゼネラルモーターズも電気自動車に注力していた。GMの新社長、フリッツ・ヘンダーソンは、今後2年以内に消費者が利用できる新しい電気自動車を発売するという野心的な目標を立てました。 彼のリーダーシップの下、電気自動車であるシボレー ボルト(プラグインハイブリッドだが、電気航続距離がある)は、生産段階に移された。しかし、数年後、ゼネラルモーターズは2011年に大規模なリストラ計画の一環として車両をリコールすることになった。 一部の旧勢力がイノベーションと変化に苦労している間、新興企業のテスラのよう な市場への新規参入者は先へと進み始めた。環境変化と革新的な技術に情熱を注ぐパイオニア、起業家、エンジニアが、新興のEVセクターのバックボーンを形成した。従来の業界の境界線の外で影の中で活動することによって、テスラは主要な自動車メーカーに対する地位を確立し、業界全体をより大きなイノベーションと競争へと押しやった。 電気自動車へのシフトは、もはや純粋に環境への配慮の結果だけではなかった。世界的に経済状況が変化するにつれて、米国、ヨーロッパ、日本の政府は、電気自動車戦略を経済再建と石油輸入への依存度を下げるためのツールと見なすようになった。EVの購入に対する新しいインセンティブとバッテリー生産への多額の投資は、大量市場への移行を推進するために実施された措置の一部である。 変化の背景に対して、このドキュメンタリーは、技術開発、政府のインセンティブの役割、消費者の行動、電気自動車市場の進化に伴う確立された自動車メーカーへの変革的な影響など、さまざまなテーマを探求する。 日産は、他のEV生産企業よりも優位に立つと考えられていた全電気リーフモデルの量産に力を入れている。 従来の生産システムとバッテリーのリサイクルを使用して電気自動車を大量生産することの課題から、 ペインのカメラは電気自動車業界を定義したすべての経験を捉えている。 日産のカルロス ゴーンは、日産の全電気リーフが最初に量産される全電気自動車になると発表し、ゼネラルモーターズがプラグイン ボルトを発表したことから、EVの爆発が目前に迫っているように思われた。 技術的、経済的、および社会的な激変に突き動かされた業界では、1つの重要な質問がドキュメンタリーに響き渡った。 主要な自動車メーカーと新規参入者は、急速に変化する市場の期待と環境に優しい車両への需要の高まりとの間で、どのように収益性のバランスを取るのだろうか? この旅は、挫折と課題に満ちていたが、電気自動車に対するコンセンサスが高まっていることを示した。電気自動車はもはや周辺技術ではなく、主流の消費者市場における実行可能な選択肢となっていた。 『電気自動車の逆襲』の中心にあるのは、テスラの起業家たちと、より環境に優しい未来への大胆な賭けだ。電気の大衆市場の出現はすぐそこまで来ている。
レビュー
おすすめ