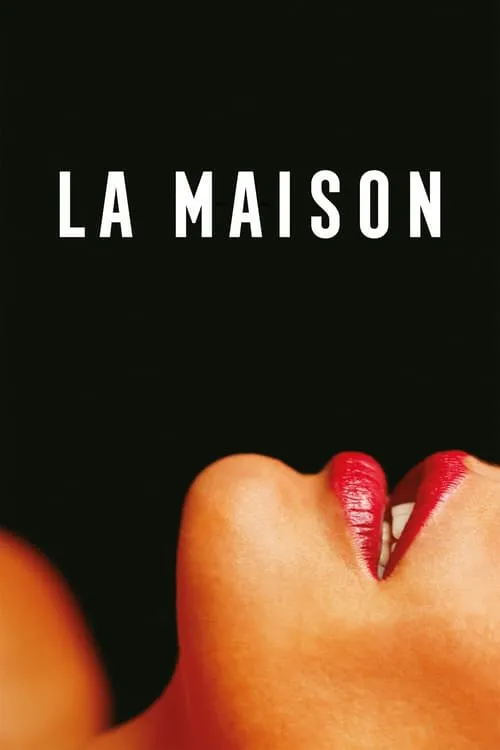La Maison:娼婦と作家
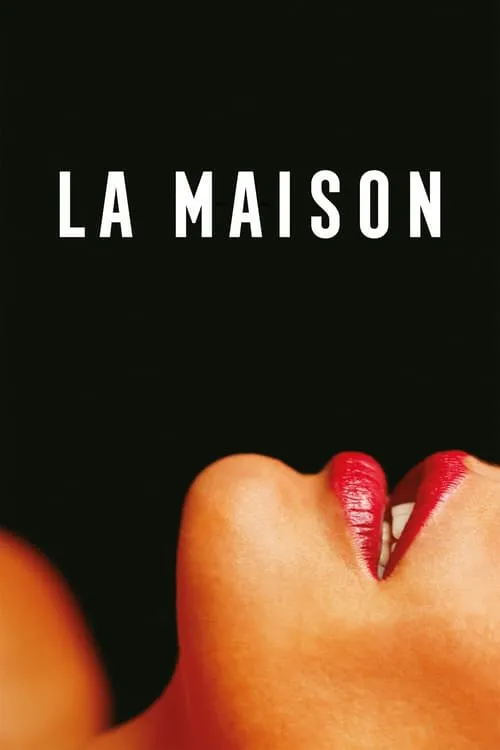
あらすじ
2017年に公開された『La Maison:娼婦と作家』は、ファニー・アラゴンとマルク・フィットゥシが脚本・監督を務めたフランスのドラマ映画である。本作は、イザベル・ユペール演じる27歳のフランス人小説家エマが、ベルリンで売春の世界を探求する物語である。彼女は、ゴンゾー・ジャーナリズムのスタイルを採用し、その主題に没頭することでより深く理解しようと、自らの経験に基づいて本を書くことを目指している。 エマは売春宿に潜入することを決意し、メディカルチェック、心理評価、長時間の面接を含む徹底的な審査を受ける。彼女の動機は多岐にわたる。彼女は、表現しようとする世界に近づきたいと考えているが、彼女の真の意図は曖昧なままである。彼女は、売春婦の生活についての小説を本当に書きたいのか、それとも自分の執筆活動を、ファンタジーに耽溺するための隠れ蓑として使っているのだろうか? エマは新しい生活に落ち着き、「アリス」という名前を使い、それぞれの複雑な物語と動機を持つ他の売春婦たちと出会う。生き残るために苦闘するロシア人女性ナジャ、虐待のサイクルから抜け出せないモロッコ人女性ナオミ、家族によって売春を強いられたインド人女性マニシャ。エマがこれらの女性たちと交流することを通して、この映画は、性産業の過酷な現実、社会的不平等、人身売買、個人の悪魔を暴き出し、人々をこの仕事へと駆り立てる。 最終的に、エマの執筆活動は後回しになり、彼女は新しい「家族」の生活にますます没頭していく。彼女の経験は当初、ほんの数週間で終わるはずだったが、2年間も滞在し、女性たちと親密な関係を築き、彼女たちの苦闘に深く関わるようになる。この間、彼女は、この決断に至った自分自身の性格の一部と向き合わなければならない。エマが滞在する主な理由は、本を書くことだけではないかもしれない。彼女の経験は、彼女自身の欲望と不安を掻き立てたのだ。 映画の撮影は、売春宿の裏社会とその居住者たちの日常を捉え、殺風景で不安を掻き立てる。カメラは、鈍い灰色の壁、狭苦しい廊下、汚れた使い古された家具に焦点を当て、登場人物たちの苦闘に暗い背景を提供している。物語が展開するにつれて、観客は、人間の本性の不快な側面に向き合うことを余儀なくされ、エマの経験と彼女が身を置く人々の生きた現実との間に類似点を見出す。 2年が経過すると、エマの新しい生活は彼女に負担をかけ始める。故郷にいる愛する人たちとの関係は悪化し始め、彼女は長期間不在の結果に直面しなければならない。その負担はますます顕著になり、彼女の容姿、気分、感情状態に現れる。エマは、自分の内面とベルリンで作り上げたペルソナとの間の不協和音に直面しなければならない。 映画全体を通して、イザベル・ユペールは、エマとして複雑でニュアンスのある演技を披露する。彼女の描写は、彼女のキャラクターの矛盾と曖昧さを前面に押し出し、彼女の動機についての陰謀を深めている。物語が終わりに近づくにつれて、エマの物語は答えよりも多くの疑問を投げかける。彼女は本当に自身の経験によって変えられたのだろうか、それとも最初に暴こうとしたファンタジーにただ深く陥っただけなのだろうか? 最終的に、『La Maison:娼婦と作家』は、性産業に閉じ込められた人々の生活について考えさせられる解説を提示し、女性たちをこの時点に導く社会的、経済的、個人的な要因に光を当てる。それは、人間の身体の商品化と、性産業の制約から抜け出すことの難しさについての痛烈な探求である。この映画はまた、エマ自身の主体性と意図について重要な疑問を投げかける。性産業についての本を書くことは、真実を求めることなのか、それとも自分の性格の暗い側面を容認してもらうことなのか?
レビュー
おすすめ