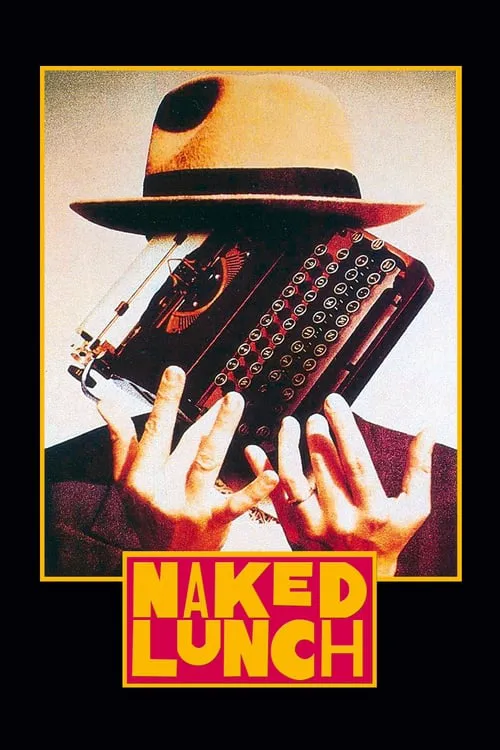裸のランチ
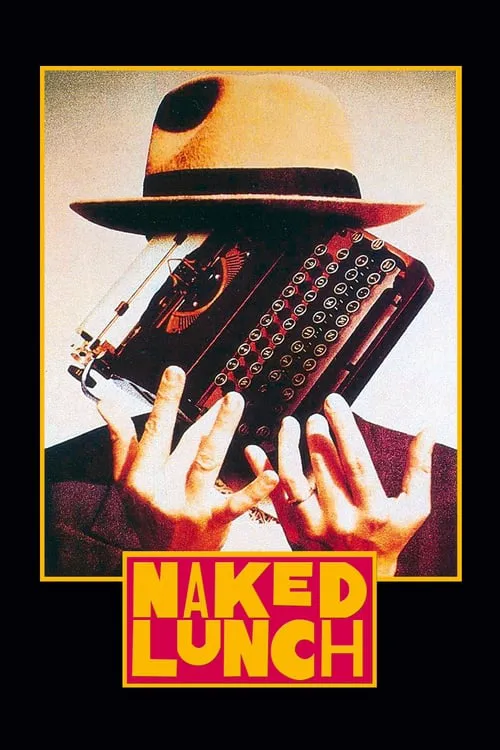
あらすじ
デヴィッド・クローネンバーグが1991年に映画化した『裸のランチ』のシュールで悪夢のような世界で、ウィリアム・S・バロウズの1959年の小説が蘇る。ピーター・ウェラーがビル・リーとして主演するこの映画は、人間の本性、中毒、そして現実とファンタジーの境界線の曖昧さという、より暗い隅々への旅へと観客を誘う。 物語は、論理的な説明を拒む幻覚、夢の風景として提示される。そこは、社会の正常なルールがもはや適用されず、自己と他者、現実とファンタジーの境界線がますます歪んでいく世界だ。害虫駆除業者のビルと妻のジョーン(ジュディ・デイヴィス)は、目的のない漂流生活を送り、ビルの殺虫剤でハイになるというお気に入りの娯楽にふける。彼らの会話はぎこちなく、彼らの交流には感情的なつながりがない。 彼らの生活は、ベンウェイ博士(イアン・ホルム演じる)という、彼らを新たな高みに連れて行くことを約束するムカデベースの物質を売り歩く謎めいた人物に出会うことで、さらに複雑になる。その夫婦は、一発キメたいと、その物質を摂取するが、それは悲惨な結果をもたらす。ジョーンの健康状態が悪化し始め、結局、奇妙な事故で死亡し、ビルは衝撃を受ける。 ビルはゴキブリに変身したタイプライターから命令を受けるようになり、彼の世界は制御不能に陥り続ける。創造的破壊の象徴であるこのゴキブリは、ビルの行動を制御し、最終的に『裸のランチ』(バロウズによる実在の本)となる一連のグロテスクで不穏な物語を書かせる。物語が展開するにつれて、ビルのより暗い衝動と欲望が明らかになる。 シュールな展開で、ビルは絶えず変容する地中海の都市にいることに気づき、そこで奇妙なキャラクターの万神殿に出会う。そこには、欲望の破壊力を体現しているように見えるファム・ファタールであるメアリー(ジュリー・カニンガム演じる)や、ビルのありそうもない味方となる苦労している作家のトム(ロイ・ローゼンバーグ演じる)がいる。 映画を通して、ビルの経験は単なる中毒と悲しみの産物ではなく、彼自身の創造的なプロセスの表れでもあることが明らかになる。彼の物語は、彼自身の潜在意識の反映であり、彼自身の心の奥底への窓だ。裸のランチが形を成すにつれて、ビルのアイデンティティはますます断片化され、現実とファンタジーの区別をするのに苦労する。 『裸のランチ』の最も印象的な側面のひとつは、その象徴主義とメタファーの使用だ。この映画は、人間の本質の複雑さを伝えるイメージとモチーフの豊かなタペストリーだ。たとえば、ムカデは、一度に複数の方向に移動できる、断片化された自己を象徴している。一方、ゴキブリは創造性の破壊的な力を象徴し、内部から社会の構造を食い荒らす。 結局のところ、『裸のランチ』は、従来の物語構造に縛られることを拒否する映画だ。それは人間の意識の地下世界を巡る夢のような旅であり、そこでは自己と他者、現実とファンタジーの境界線がますます曖昧になる。映画が終わりに近づくにつれて、ビルのアイデンティティは単なる殻、彼を突き動かす相反する欲望と衝動のための空洞化された器にまで縮小される。裸のランチは、人間の精神の最も暗い奥底を明らかにする芸術の力を証明するものであり、デヴィッド・クローネンバーグの卓越した映画化は、バロウズの小説をそのシュールで悪夢のような栄光の中でよみがえらせる。
レビュー
おすすめ